貯金、してますか?
貯金している人も、貯金していない人も、「お金は将来のために貯めないといけない」と漠然と考えている人は多いと思います。
今回紹介する「DIE WITH ZERO」は、そんな「漠然と将来のために貯金する」ことに疑問を呈し、「そもそも何のために貯金しているのか」「その貯金はいつ使うのか」を考えるきっかけをくれる本です。
結果的に、「今日、今の時間をどのように使うか」まで突き詰めた、今日から人生を変えうる一冊です。
早速まとめていきましょう。
ひとことまとめ
この本を一言で言うと、
お金を稼ぐことと使うことの意味を根本から考え直し、本当に充実した人生を歩むための考え方を提案してくれる本です。
二行要約
本書の概要を2行で説明すると、だいたいこういうことを言っています。
- 『アリとキリギリス』という童話がある。多くの人が「キリギリス的な生き方」より「アリ的な生き方」が正しいと思っているが、本当にそうだろうか?アリは一体、いつ遊ぶことができるのだろうか?
- 金を使い切らずに死ぬことは、「使わなかった金を稼ぐために費やした時間」を無駄にすることに他ならない。人生の最大化のために、経験に金を使い、ゼロで死ぬことが最も効率的である。
わたしたちは子どもの頃から、「将来に向けて貯金をする」事が正しい事であると教育を受けてきました。浪費は悪であり、倹約は美徳であると。
著者のいるアメリカでは、老後に向けて貯金をすると言いつつも
老後には貯めた金を使わず、多額の資産を残して亡くなる方が後を絶たないと言います。
そんな中で、本当に充実した人生を歩むための金の使い方、すなわち人生の各ステージにおける金の貯め方、使い方についてさまざまな切り口から考察しているのが本書です。
金は大切だが、モノや経験に交換しないと何の意味もない
金は大切で有限なものではありますが、貯めているだけでは全く意味がありません。
筆者は金をモノよりも「経験」に交換することを勧めています。
さらに、「経験」は年齢によってその意味や感じ方が変わるため、多くの事は後回しにしない方が良い、と説いています。
あらゆる経験には期日があり、「将来いくらでも出来ること」などないということに気づかせてくれます。
厳選ポイント3つ
金の「一番いい使い方」を考えよう
前提:ライフエネルギーという考え方
金は自分の時間を使って得るもの。
例えばモノを買うとき、自分の仕事で何時間分の値段かを考える。
「この服を買うために、3時間働けるだろうか?」
自分の時間を金に交換し、その金をモノや経験に交換するように、エネルギーが流れるイメージを「ライフエネルギー」と表現しています。
金は「良い経験」に使え
筆者は金を「ポジティブな経験 」に使うことを推奨しています。
特に若いうちにポジティブな経験をしておくことで、
その思い出が与えてくれるポジティブな影響を「思い出の複利効果」と表現していて、
思い出がずっと、自分にポジティブな影響を与えてくれます。
若いうちに、「良い経験に投資する」のが良いと、本書では言っています。
すべての経験には「期日」がある
いつまでも子ども用プールで遊べると思うな。
大人になると、子ども用プールでは遊べなくなります。
もちろん、買ってくれば物理的には遊ぼうと思えば遊べますが、
最も楽しめる時期は過ぎているところがポイントです。
他のすべての経験(例えば登山、スキー、旅行など)も、必ず「最後の1回」の日がやってきます。
それは、物理的に実行不可能になることもあれば、楽しみを最大に引き出せる時期を過ぎてしまうという意味も含まれます。
終わりを意識する
退職の前の1週間、部活動の引退試合、学校生活で最後の授業。
そういった「最後のシーン」で幸福感がアップしたり、モチベーションが上がるような感覚に覚えがある人は多いかも知れません。
人生においても終わりを意識することで同じような効果が得られ、今日を充実した日にするためのヒントを得ることができます。
明日死ぬとしたら今日をどう生きるか?3日後なら?1ヶ月後、半年後ならどうだろう?
必要以上に貯金することの無意味さ
若いうちに「はした金」を貯めるな
10万円の価値は、今が一番高い
例えば子どもの頃、1000円は大金でした。
お菓子でもなんでも、たくさん買うことができました。
大人になれば、1000円でお菓子を買うことはできるものの
子どもの頃ほどには幸せを享受することができないことは想像に難くないでしょう。
若い頃に頑張って倹約して10万円を貯めることは、
小さな子どもが1000円を貯金したまま大人になってしまうようなものです。
10万円の価値は年々下がる
一般的に、給料は年齢とともに上がっていくため、
多くの人が、将来的には(若いときほどには)無理せずに、
10万円を貯めることができるようになります。
将来の「金銭的に余裕がある、歳とった自分」が、今の「若くて貧しい自分」から10万円を巻き上げているところを想像すると、人生を俯瞰してみた時にどれだけ勿体ないことをしているのか、イメージしやすいでしょう。
給料の○%を貯金する という罠
また筆者は、「年齢に関わらず給料の○%を貯金する」という考え方も良くないといいます。
例えば将来、月の給料が40万円になったとき、
25%にあたる10万円を毎月貯金することはできるかもしれません。
しかし若い時に月の給料が15万円なのに、同じ25%の37,500円を貯金するとなると
貴重な若い時間を「はした金を貯めるために」倹約生活で過ごしてしまうことになると本書では訴えています。
人はいつか死ぬ
人生はゲームのように、リザルト画面に表示される貯金額を競うようなモノではない。
それなのに、人は死ぬまで貯金をし続ける。人生が無限に続くような気持ちで。
老後に備えすぎる人たち
多くの人が「老後のために」貯金をすると言っています。
しかし筆者の調査によると、70歳になってもまだ貯金している人は多く、
実際の使用状況を見ても、老後にお金をあまり使わない傾向が見られるとのことです。
この結果を筆者は、歳をとると金を使う意欲自体が下がるようだ、と分析しています。
実際に、筆者がおばあちゃんにお祝いのために1万ドル(約100万円)の小切手をプレゼントした時、おばあちゃんは自分のためには全く使わず、孫へのプレゼントを買うための50ドルだけしか使わなかったエピソードが紹介されています。
エイリアンの襲来に備えて貯金をする人はいない
高額な終末医療に備えるために貯金をしている、という意見もあるようです。
しかし多くの場合それは非常に高額で、個人で備えるには高すぎるものが多いです。
大きな犠牲(時間や健康)を払って貯金をしても、
ほんの数日から長くて数ヶ月の治療費にすべて消えていくことになる。
個人がどれだけ貯金をしても太刀打ちできるはずがない、そんな高額な医療のことを筆者は「エイリアンの襲来」と喩えています。
人はいつか死ぬのに、最後の数日間、数週間の延命のために、どれだけ働くつもりなのか?
高度な終末医療のために貯金をするというのは、
どうせ勝ち目のない戦いのために人生を浪費してしまうことであって、苦労に見合わない選択であると言えます。
貯金し続けて死んだ人の金はどこへ行くのか
貯金し続けた人が残した金の辿る道は2つ。相続と寄付です。
相続
本書の考えによると、親が亡くなった時の相続は「良くない金の渡し方」に当たるといいます。理由は以下。
- 親が亡くなる時、多くのケースでは子どもも高齢になっている
子どもにとっての「金の価値を最大限引き出せる若さ」は過ぎている状態。
子どもにとって金の価値がとても下がった状態で受け継ぐことになる。 - 本当に必要な時に与えられない
親の死という偶然に任せて相続するのではなく、いつか子どもに与えるならば、
子どもが支援を必要としている時に、親が生きている間に与える方が、子どもにとっても親子関係にとっても良い影響があると筆者は言っている。
寄付
特にアメリカでは、死後に貯金を寄付する人は多いようです。
しかし、これも本当に最適なタイミングではないと筆者はいいます。理由は以下。
- 渡す側は、死ぬまでその富を抱えた状態で使わない=社会に還元する事もなく暮らしている。
- もらう側も、本当に必要としているタイミングではなく、寄付者が亡くなったタイミングで受け取ることになる。しかし支援を欲しているのは「今」であって、「あなたが死んだ時」ではない。
- もらった側は感謝を伝えることもできない。
死後の寄付には、何もいいことはない。生きている間にあげれば良い。
使わない金を稼ぐために、3年間タダ働きした人
本書はアメリカの本なのでアメリカの経済をベースに書かれています。興味深いたとえ話があったので、ここではイメージしやすいように、日本円に換算して紹介します。
今回登場する架空の人物の概要は以下:
- 年収は平均より高い600万円
- 65歳の定年まで質素な生活
- マイホームを含む資産が定年時点で7700万円ある
- 年間の生活費は320万円
この人は定年後から資産の7700万円を切り崩せば、働かなくても24年間生活できる計算になります。
しかし、仮にこの人物が20年後の85歳で亡くなったとしたら、使わずに残る金は1300万円。
時給二千円換算で6500時間、すなわち約3年間「使わない金」のために働いたことになる。
人生の貴重な時間とエネルギーを、もっと別の事に使えたかもしれないのに。
これでは勿体ないですよね。
資産を減らすタイミングをしっかりと考えること
本書では、貯金すること自体を否定しているわけではありません。
しかしせっかく貯金しても、きちんと使わないなら貯金の意味がない、と言っています。
最低限の貯金をして生活できる状態を保ちながら、
効果的に金を使って人生を豊かにしていくために、「きちんと金を使え」と言っているわけです。
人生のどこかで「貯金を減らし始める」ことを意識しておく
いつから資産を減らし始めれば良いのか?
その答えは、最も長生きをした時の年齢を考え、そこまでにどれくらい金を使うのか計算すると良いと言います。
人生のある日までは貯金をすればよいですが、
ある時「使って、減らしていく」フェーズに入る日が来ることを明確にイメージしておき、
意識的に「増える金」より「使う金」が多くなるようにしないといけません。
そうしないと減らないからです。
本書内では、どのように計算して取り崩していくべきか紹介されていますが、ベースがアメリカ経済の説明である点と、ある程度の金融知識が必要なため、割愛しておきます。
一応、日本で同様の運用は可能ですが、多少の勉強が必要かもしれません。
健康・時間・金のバランス
健康と時間、金の間には相関関係がある
若い時に金に傾倒(すなわち、働きすぎ、倹約しすぎ)すると、将来的に健康を損なってしまいます。
将来的に大きな損失を被ることになることは、想像に難くないでしょう。
逆に、若いうちに健康に投資(金と時間を使う)すれば、人生トータルでのコストが抑えられることもわかると思います。
健康で若いうちに金を使う方が、金の価値を引き出せる
例えば旅行に行くなら、
体が思うように動かなくなってからより、元気に活動できる間に行く方が
同じお金を使うにしても、より楽しみを引き出すことができます。
しかしタイミングが重要なものもあって、
例えばラスベガスに旅行に行くなら、若いうちの貧乏旅行よりは金銭的に余裕ができてから行く方が楽しめるかもしれません。
大事なのは「早く実行する」ことではなく、「楽しみを最大化できるタイミングで実行する」ことです。
時間を作るために金を払う人は、それが人生の満足度を上げることを知っている
夜行バスではなく新幹線を使う、電車ではなくタクシーを使う、全自動の家電や家事代行を導入するなど、時間を作るために金を払う人は、そのことで人生の満足度が上がることを認識しています。
基本的に、時間は戻すことができない貴重なものだからこそ、
時短になるアイテムやサービスのために金を使うことは、有効な使い方の一つと言えます。
総括:これからの行動1個
「経験」に投資する
本書の中で言われている「金を使え」という内容は、当然ですが「何でもいいから浪費せよ」という意味合いではありません。
しっかりと自分のライフエネルギーを使う先を選んで、「ただ貯める」ことを盲目的に行うのではなく自覚的に「今しかできない経験」に使うということです。
残りの人生で一番若い日は今日ですから、今日しかできないことは何か?という考え方を持って、お金の使い道を考えていきたいですね。
あと語り
貯金ばかりせずに金を使えと言われても、
そもそも貯金すらそんなにできてないよ。
不景気な現代社会ですから、実際にはそんな人も多いと思うんです。
でも、この本が教えてくれることの本質は「とにかく使え」ではなくて、「しっかり考えて使え」ということです。
なので、現在そんなに貯金できてないよ!?という人にも参考になる本です。
景気が良くても悪くても、給料が高くても安くても、
「今しかできないこと」は次々と終わっていき、自分はどんどん歳をとっていく。
その現実は変わらない。その中で何をするか。
今から変えられることを変えて、より良い人生を送りたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
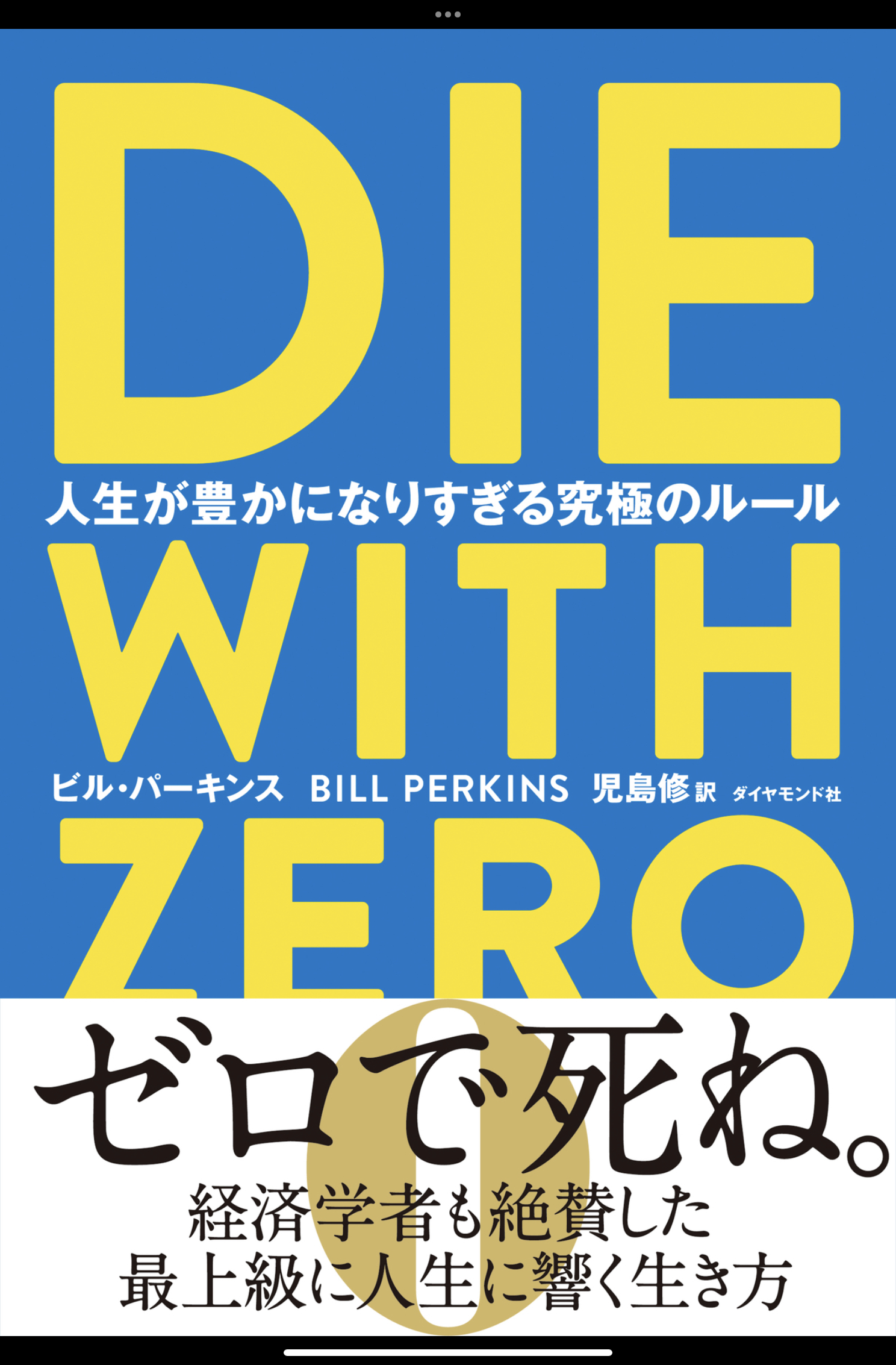


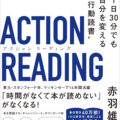

コメント