あなたは時間、足りてますか?
多くの人は、やりたいことが沢山あるのに時間が足りない と悩んでいます。
そんな悩みを解消すべく「こうすれば効率的にものごとを進めることができる」といった時間術スキルの本や、「やりたいことをやるために、やりたくないことを切り捨てなさい」といった刺激的なメソッドまで、世の中には多くのアイデアが溢れています。
しかし、その本を読んでもうまく行かなかった人や、
一時的にはうまく行ったもののしばらく経つとまた時間に追われる生活に戻ってしまった、という人も多いのではないでしょうか。
今回はそんな悩みに切り込み、
「時間術なんてだいたいどれも根拠もないし効かない」と説く面白い本を紹介します。
さっそくいきましょう。
ひとことまとめ
この本を一言で言うと、
多くの研究で、「これまでの時間術は万人には効果がない」ことがわかっている。一方で、「一部の人に効果があった」こともわかっている。それならば、どんな人にどんな時間術が効くかがわかれば、自分にあった時間術を選ぶことができるのではないか?という切り口で、それぞれの「時間感覚」に合った時間術を紹介してくれる本です。
二行要約
本書の内容のポイントをざっくり2つ紹介します。
大事なのは時間管理ではなく「時間感覚」
これまで試した時間術やスキル、タスク管理、スケジュール管理がうまく行かなくても、落ち込むことはない。それらはほとんどの人に効かないのだ。自分のタイプを把握して、自分にあった時間術を試し、時間感覚を調整していくと良い。
時間を効率的に使うのではなく、時間についての体質を改善する
どれだけ時間を上手に使えるようになっても、「時間を効率的に使おう」としている限り、効率よく時間を使えるようにはならない。時間感覚を調整し、いつも何かに追われているような焦りと不安の感覚を捨て、時間についての”体質”を改善することが本書のゴールである。
解説
本書は、世界中のあらゆる時間術に関する論文を読み込んだ著者が、4063ものデータから導き出した時間術の本質を提唱している本です。
- 時間術はだいたい効果がない
- 時間術を駆使しても仕事のパフォーマンスはさほど上がらない
- 時間の効率を気にすればするほど作業効率は下がる
- そもそも時間をマネジメントすることなどできない
という衝撃の序章から始まります。
もう打つ手は無いのか?
それでは、どうしようもないのか?というとそうではありません。
本書ではそもそも「時間」とは何か?というところから切り込みます。
著者は「時間とは、過去を想起し、未来を予期することで、自分の過去と未来を”連続したものであると認識する”人間の感覚によって知覚されるもの」であると解説します。
つまり、
- 「さっきお昼ごはんにラーメンを食べた。味はこんな感じで、量は多かったな」と過去を覚えていて、
- 「明日は仕事だ。何時に家を出て電車に乗って、PCを開いて…」と未来を考えること。
過去を思い出し、未来までを連続したものとして思い浮かべることが「時間感覚」だということです。
この「時間の定義」を踏まえたうえで、時間をコントロールするのではなく、「自分の感覚に合わせた時間の使い方」に調整していくことで、思い通りの時間を過ごすことにつながるということです。
厳選ポイント3つ
「時間」とは、過去を思い出す「想起」と、未来を思い描く「予期」でできている
人間には時間を知覚する器官は存在しない
人間には時間を感知する器官が備わっていません。
にもかかわらず、我々は時間が経過しているのだと感じています。
なぜ、時間が経過してきたように感じるかというと、記憶があるからです。
昨日あの場所に行った。今朝は7時に起きて、今日のお昼にラーメンを食べた。
そういった記憶があることで、「以前から続いている時間」を知覚出来ていると言えます。
記憶をとどめておけない人は、時間を認識できない
本書内では、怪我や病気で脳に損傷が発生し、20分より前のことが思い出せない人の例が紹介されています。
その人は、20分より以前の記憶がないため、昨日から今朝、今へと続く時間の流れを認識していないことになります。そして、「20分しか記憶をとどめておけない人」は、未来を想像することもできなくなっていたそうです。
未来を想像するための過去の記憶がないためだと考えられます。
よって、記憶を保持できない状態の人の感覚には「今」しかない。ということが言えます。
昔の記憶(想起)から未来を予測(予期)することが、過去と未来すなわち時間の本質
たとえば、「大きな声で怒られた」という目の前の現実があるとして、
「過去に大きな声を出したとき、この人は怒っていた。その時は謝ったら許してくれた(想起)」
「今回も謝ってみよう。おそらく許してくれるだろう(予期)」
わたしたちの脳はこういった判断を瞬時に行い、想起と予期を組み合わせて、
以前に怒られた過去とこれから許されるであろう未来を「時間」として認識するわけです。
想起がズレていたり、予期が多すぎるなど、人によって時間の捉え方=時間感覚は異なる
予期と想起にはクセが出る
たとえば「会議の資料を作っておいて」と指示されたとき、
「前回の会議資料を作るのに4時間かかったな(想起)」
「だから、今回も4時間でできるだろう(予期)」
という思考がまずあるとします。
しかし実際には、以前にその資料を作ったときにかかった時間は6時間でしたが、記憶を都合よく解釈していたり、上司の助けを得てたまたまうまく行っただけなのに自分のチカラだけで4時間で仕上げたように錯覚する人がいます。
これは悪いことではなく、誰にでも多かれ少なかれ存在するズレです。
当然、4時間で終わると思って取り組んだものの、実力としては6時間かかる作業なので、「なぜか時間が足りない!」といって苦しむのです。そこにズレがあるわけです。
「時間が足りない」の正体のひとつは、この想起のズレからくる「予期の誤り」です。
予期と想起のクセには個人差がある
また、下記のように別の捉え方をする人もいるでしょう。
「前回は忙しい中でも4時間で出来たから、今回は3時間で出来るだろう(想起が肯定的すぎる、予期が薄い)」
「前回4時間で出来たと思っているけれど、先輩に助けてもらったから一人では何日かかるかわからない。ほかにもやることがあるのに、どうしよう…!(想起が否定的で、予期が多すぎる)」
このように、想起と予期の特性には個人差があって、それぞれがうまく仕事を進めるためにはそれぞれのタイプに適した時間術を使う必要があるといいます。
自分は想起が楽観的すぎて、過去にとても苦戦した作業を「簡単にできた」と思い込む節があるな。
自分は予期が多すぎて、これからやることがたくさんあるように感じて動き出せないことがある。
こういった自分の特性を把握して適した時間術を使っていくことで、自分の時間をある程度思った通りに使うことができる状態に近づきます。
効率を求めると効率は落ちる
予期と想起のズレを調整することで、自分の時間をコントロールして使うことが出来るようになっていく。しかし効率化を追い求めてはいけない。
研究が示す残酷な真実
著者が数多くの研究をまとめたところによると、「時間を効率的に使おう」とすればするほど、効率は下がっていくという研究結果が多数報告されています。
その一例として、「時間を効率的に使わなければ」と思いすぎるあまり、目の前の時間の使い方に集中してしまう弊害として、「拡散的思考」の重要さを説いています。
たとえば、シャワーを浴びているときに新しいアイデアをひらめいたり、布団に入った瞬間に重要な予定を思い出して慌てたりすることがあります。このときのリラックスした脳は「拡散的思考」に切り替わっているわけです。
しかし、「時間を意識する」という行いは拡散的思考の逆である「収束的思考」であり、人間は拡散と収束を同時に行うことはできません。
つまり、時間を気にすること自体が、脳のリラックスした活動を阻害する行いであるため、結果として効率は落ちてしまうということになります。
退屈に耐えられない現代人
現代人は「待つことができない」「退屈を受け入れられない」という、高度に高速化し情報が溢れた世界に暮らしている弊害を受けています。
それによって、時間を効率的に使おうとして、結果的に時間を効率的に使えないという悪循環に陥っているということを指摘しています。
本書内では、退屈を受け入れるためのいくつかの提案がされており、時間という概念と向き合うために欠かせない視点を与えてくれます。
自分のタイプ
わたしのタイプ診断では、「予期が濃くて多い容量超過型」「想起が正しく肯定的な自信家型」となっています。
予期タイプ:容量超過型
このタイプは、つねに複数の作業に追われており、焦りや不安、圧倒される感覚に襲われやすいタイプです。そのため、決して時間の使い方が下手なわけではないものの、つねに自分の行動に不満を抱き続けます。
想起タイプ:自信家型
自己効力感が高いため、難しい作業にも臆せず取り組めるタイプです。ただし、自分の能力を信じすぎ、必要な助けやリソースを得られずに失敗することもあります。
タイプにあった対応をとる
そこで、「プレコミットメント」という「事前に遊びの予定を入れておく」という手法と、
「SSCエクササイズ」という自分のタスクの優先順位をより緻密に検討する手法を取り入れてみたいと思います。
どちらもやや大変そうではありますが、自分の特性にあった方法として紹介されているので、手当たりしだいに全部試すよりは精度が高そうです。
ちなみにタイプ診断はWebでも行うことが可能です。ぜひやってみてください。

あと語り
単なる時間術の本だと思って開きましたが、あまりの面白さに一気に読み切ってしまった本でした。
本書にはたくさんの時間術が「こういった人にはこれが向いている」といった解説付きで紹介されています。
ただし、いずれの方法も簡単ではなく、ややトレーニングが必要な内容になっています。
だれに対しても効く万能の時間術はなく、さらに「効率をあげようとすること自体」が効率を下げる原因になっているという研究まで提示されてしまえば、素人である我々が「それでも時間をコントロールするのだ」と息巻いても、それこそ時間の無駄だと思えます。
なかなか受け入れがたいことを言っているように見える本書ですが、序盤で著者はこんなことを言っています。
余談ながら、筆者も本書の内容から大きな恩恵を受けており、いままでは年に1冊の自著を書くのがせいぜいだったのが、近年は年間3〜4冊を出せるまでスピードが上がりました。
それと同時に、1日に平均で15本の論文を読みつつ、2万〜4万文字の原稿を書き、定期的に1回90分〜l20分の動画配信をするなど、従来どおりのルーチンも乱れていません。
だからといってプライベートを犠牲にするでもなく、睡眠や運動の時間は一切減らしていませんし、読書、映画、楽器の練習といった趣味を楽しむための余裕も十分に確保できています。それもこれも、"時間感覚"にもとづいて、日々の暮らしを組み直したおかげです。
このように膨大なデータを閲覧し、まとめ、多くの著書を書いている人が効果を実感しているとあれば、一度試してみる価値はあるように思います。
いろいろな方法を試しては挫折してきた人には、ぜひ本書をお手にとっていただきたいと思っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
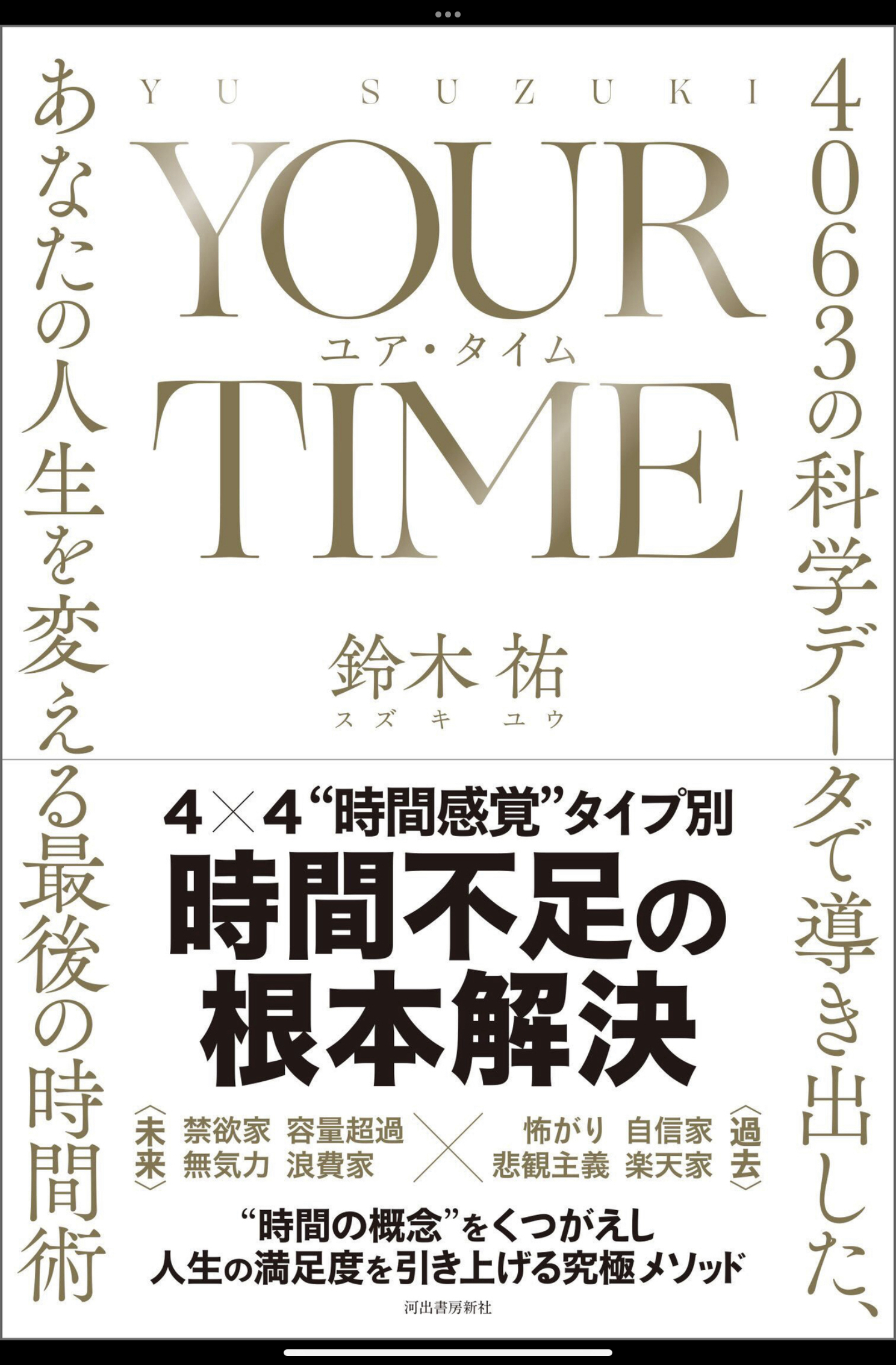


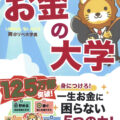

コメント